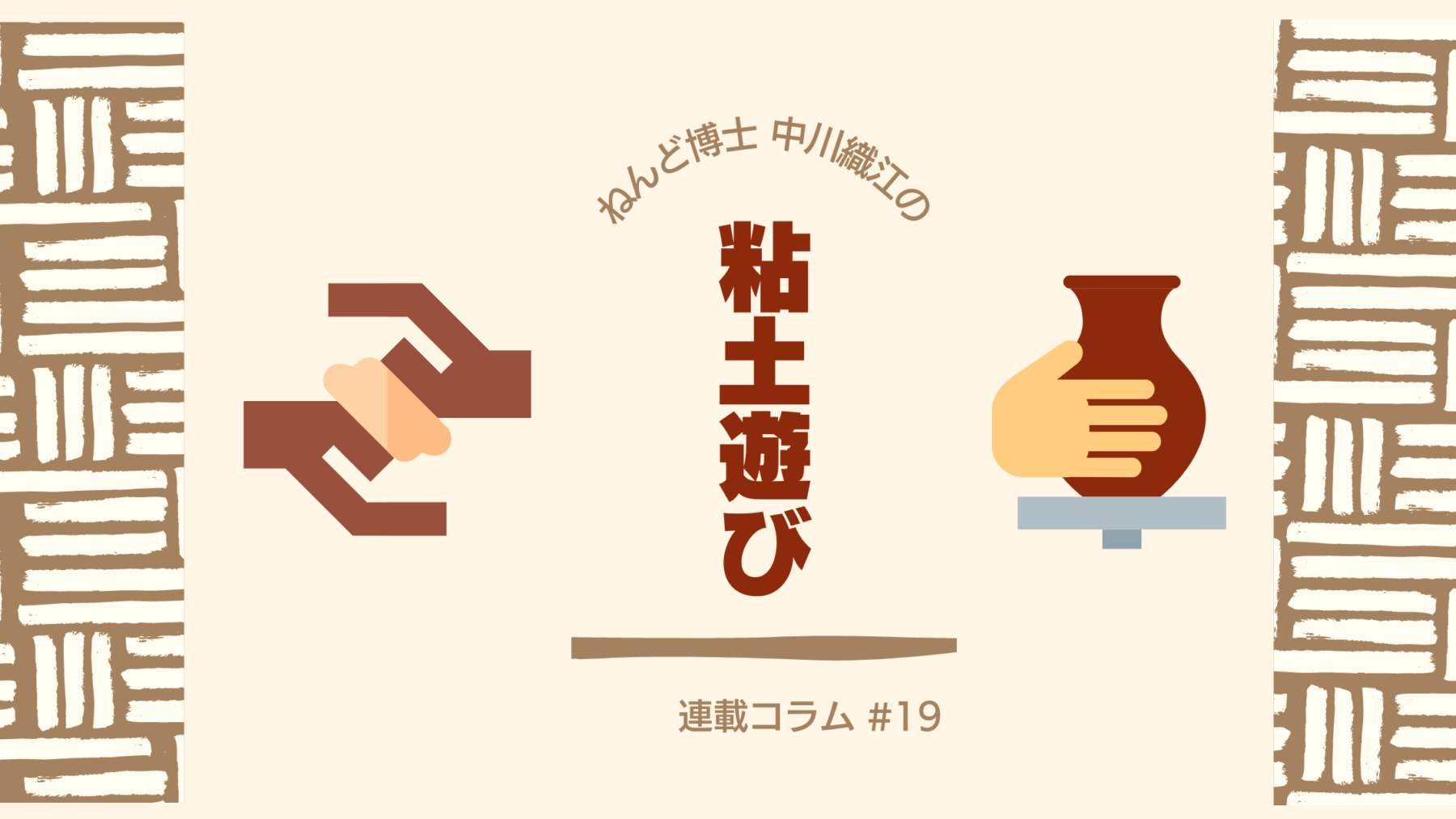よく、「絵を描かなくても、粘土遊びをしなくても、歌わなくても生きていける」と言われます。
でもわたしは違うと思います。
アートは希望の最高の形です。
こう断言できるのは、第二次世界大戦の時、ユダヤ人収容所に入れられた子どもたちが描いた絵の展覧会をじっさいに見たからです。
収容所に送られた人の中に絵の先生がいて、絵の道具をかくし持っていた。
彼女はナチスの監視員に見つからぬよう、それを子どもたちに与え、ゴミ箱に捨てられた紙類をのばし、そこに描かせた。
子どもたちは「ちょうちょ」や「トンボ」、「虹」、「花」、さまざま描いた。
ついに戦争が終わった。
生き残った子どもたちは大人になり、後年、収容所での生活をふりかえってこう語った。
「収容所という極限状態にいて、絵が希望でした。絵を描くのは希望を描くこと。強い希望があったから生きのびることができました。でなければ絶望にうちのめされて生きることは叶いませんでした」。
この「収容所の子どもたちの絵の展覧会」を企画されたのは、野村路子さん。ノンフィクション作家です。
わたしは埼玉県へ展覧会を見にいき、茨城県での講演を聞きにいき、教育雑誌の企画で対談し(残念ながら記事にはなりませんでしたが)、ご自宅へもうかがわせていただきました。
野村さんの言葉はまっすぐで、
「海外へ行ったときに、これらの絵を見てショックを受け、日本へ持っていこう、この絵の展覧会を開こう、かならず日本人に伝えようと誓い、それを自分の使命としました」。
そのお話を聞きながら、わたしは、子どもたちは収容所の中で、指で地面に線を引いたり、土をこねて人形をつくったり、泥んこをすくったりしたに違いないと思い、土遊びをしている子どもたちの姿が幻のように浮かんできました。
2011年、東日本大震災が発生した時、水や食べ物、寝る場所、暖かい部屋を何とかしようと、全国から大勢の人が応援にかけつけました。
ある歌手は、歌は役に立たないと思いつつも、勇気をふるって現地へ出かけて歌った。すると聞いている人たちが涙ぐみながら笑顔になった。下を向いていた顔が少し上向いた。歌を聞いている間だけは悲しみを忘れているように思えた。
紙とクレヨンを持って臨時に絵画教室を開いた人たちも、手を動かそうと手芸の会を開いた人たちもいました。歌を聞いても絵を描いてもお腹はいっぱいにはならない。でも心が和らぐ、元気をもらえる、つらい現実が薄らぐ、希望が生まれる。
心も、体と同じように栄養をほしがっている。
安心したい時、わたしは粘土遊びをします。
立体の粘土は、何よりも実感があります。手で触ると手応えがあり、柔らかく、思い通りの形になってくれます。こねているとじわじわと心がラクになります。これでいいのだ。